子どもの予防接種ガイド
大人の予防接種についてはこちらをご覧ください。
新着
- 海外で麻しん(はしか)がたいへん流行しています。
麻しんの感染力は非常に強く、空気感染等により、簡単に人から人へ感染します。また、麻しんの免疫が不十分な人が感染すると、高い確率で発症します。
今後、海外からの輸入が増え、それによる国内での感染伝播の可能性があることから、特に定期接種対象の方(1歳児と年長児)はできるだけお早目の接種をご検討ください。(令和6年2月28日) - 武田薬品工業株式会社が製造販売しているMR(麻しん風しん混合)ワクチンの一部ロットにおいて自主回収が行われる見込です。自主回収の詳細につきましてはこちらをご覧ください。
厚生労働省によりますとワクチンの不足は生じない見込みとなっておりますが、一時的に供給が不安定となる可能性もあります。接種を検討されている場合は、お早めに医療機関にご相談ください。(令和6年1月19日) - 本来の定期予防接種期間の末日を含む期間に、新型コロナウイルス感染症に罹患又は、濃厚接触者となり外出が制限されていた場合等の理由で、やむを得ず定期の予防接種の機会を逸した方は、事前に申請をしていただくことで、定期予防接種として接種できる場合があります。詳しくは健康づくり課までお問い合わせください。(令和5年5月19日)
- MR(麻しん風しん混合)2期、日本脳炎(年度年齢18歳の方)の予診票を送付しました。(令和5年4月1日)
- 9価HPV(子宮頸がん予防)ワクチンが4月1日より定期接種化されました。詳細はこちらです。(令和5年4月1日)
目次
1.予防接種の種類・予防接種スケジュール
病気の説明、対象年齢、標準的な接種時期等については、各ワクチンのページをご覧ください。
異なるワクチン間の接種間隔についてはこちらのページをご覧ください。
定期予防接種A類(対象年齢の期間内の場合、無料※全額公費助成)
古河市が助成をしている任意予防接種(対象年齢の期間内の場合、一部助成※自己負担あり)
予防接種スケジュール
R6予防接種スケジュール (PDFファイル: 609.7KB)
2.予防接種の受け方
(1)古河市契約医療機関で接種する場合(一部市外あり)
以下一覧の中から医療機関を選び、医療機関に直接連絡し、事前に予約してください。
古河市契約医療機関一覧(R6.3現在)(PDFファイル:731.5KB)
※茨城県内で接種する場合
こちら(茨城県内定期予防接種協力医療機関)に記載のある医療機関で、接種したい予防接種の項目に「○」がついている場合は、お手続きなしで接種可能です。直接、医療機関へ予約してください。
(2)県外・市外等、古河市契約医療機関以外で接種する場合(里帰り等)
里帰り・かかりつけ等の理由により、古河市契約医療機関以外で接種をする場合、接種費用は償還払い(全額自己負担で接種、後日口座へ還付)になります。
接種の際には、医療機関宛ての依頼書が必要となります。健康づくり課で接種前に事前申請が必要です。(申請の流れについては下記をご覧ください。)
※小児任意予防接種(おたふくかぜ・小児インフルエンザ)は申請方法が異なりますので、こちらをご覧ください。
※郵送申請の場合、依頼書の到着まで10日程度(土日除く)要する場合がありますので、余裕をもって申請または医療機関の予約をしていただきますようお願いいたします。
申請の流れ
- 下記のリンクから申請書をダウンロードし、郵送または窓口にてご提出ください。
- 予防接種依頼書交付申請書(PDFファイル:100.9KB)
- 予防接種依頼書交付申請書(Wordファイル:20.9KB)
- 記入例(PDFファイル:314.6KB)
※お急ぎの方は、健康づくり課窓口でお手続きください。
※ダウンロードが難しい場合は様式をご自宅にお送りいたしますので、ご連絡ください。
- 健康づくり課から必要書類(医療機関宛ての予防接種依頼書・請求書・添付書類一覧等)を郵送します。
- 必要書類を医療機関へ持参し、全額自己負担で接種してください。
- 請求書とともに領収書等を添付の上、ご提出ください。後日、口座にお振込みいたします。(領収書等に、氏名・ワクチン名・金額が書かれているかご確認ください。)
請求期限
申請後、予防接種をした日から1年以内
申請場所(窓口または郵送)
健康づくり課 感染症対策係(古河福祉の森会館内)
〒306-0423
古河市新久田271-1
3.接種当日の持ち物・注意事項
接種当日の持ち物
母子健康手帳・予診票・保険証
接種の注意事項
- 医療機関には、お子さんの状態がわかる保護者が連れていきましょう。
- 予防接種はそれぞれ対象年齢と接種回数・間隔が決められています。決められた年齢・回数間隔を守って、接種を受けましょう。
- 接種時に古河市に住民票がない場合(古河市から転出した当日から)公費で接種を受けることができません。詳細はこちらをご覧ください。
4.予診票送付時期について
- 出生6週・・予診票綴(おおよそ5歳までに受けることができる予診票が綴られています)
- 年長・・MR(麻しん風しん混合)2期
- 9歳・・日本脳炎2期
- 11歳・・二種混合
- 13歳・・HPV(子宮頸がん予防)ワクチン
予診票がお手元にない場合や紛失された場合は、健康づくり課までお問い合わせください。
5.予防接種による健康被害と救済制度
予防接種による健康被害と救済制度についてはこちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 健康づくり課 感染症対策係
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6882
ファックス:0280-48-6876
健康づくり課へのお問い合わせ












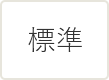
更新日:2024年04月01日