自主防災組織
自主防災組織とは
自然や人為的による災害が発生した場合、その規模によっては消防・行政などの救助活動・支援が間に合わないことが考えられます。こうした災害時の被害拡大を防止し、軽減するためには、身近な地域住民による初期の防災活動が最も有効的となります。そこでは、個々のばらばらの活動よりも組織として集約された力の方がはるかに有効になり、災害時機敏に対応でき、被害の拡大を防ぐことができます。いざという時に地域住民が『自分たちのまちは、自分たちで守ろう!』という連帯意識を持って組織し、日頃から災害時における役割分担等を決めておき、防災に関する啓発・防災資機材の整備・防災訓練を積み重ねておくことが必要です。 このことについて市では、自主防災組織の結成を推進しており、令和3年度末現在、144の自治会・行政区などにおいて結成がされております。 つきましては、未結成の自治会・行政区におかれましては、災害に備えて安心して生活できる地域づくりの一環として、組織化についてご検討をいただきたいと思います。
自主防災組織を結成する場合の組織構成(例)
防災活動のための組織づくりには、地域の実情に合わせて既存の地域の組織を活用する方法と防災活動のため新規集団を結成する方法があります。
(自治会・行政区ごとを単位とします。)結成例
例1 行政区や町内会がそのまま自主防災会となる場合
- 自主防災本部
※行政区長、副区長、会計等で本部を構成し行政区長は防災会長を兼ねる。 - 町内会長
※町内会長は、本部の指揮により、広報・防火・避難・誘導・救護等の長を兼ねる。 - 班長
※班長は町内会長の指揮により、各班に分担された防災活動の責任者として活動する。 - 世帯
※各世帯は班長の指示により行動する。
例2 行政区や町内会の組織とは別に自主防災会を結成する場合
- 自主防災本部
※防災会長を中心に、本部を構成する。 - 広報部長(班長)
防火部長(班長)
救出救護部長(班長)
避難誘導部長(班長)
※各部長または各班長は役割分担により、本部の指揮により、防災活動を行う。 - 部員(班員)
※部員または班員は部長(班長)の指揮により、防災活動を行う。 - 世帯
※各世帯は部員(班員)の指示により行動する。
自主防災組織を結成するには
「古河市自主防災会組織活動育成事業補助金」について
1 補助金の種類
- 結成事業 1組織10万円(定額)
- 資機材等整備事業 1組織40万円(1/2補助)
- 運営事業 1組織3万円(1/2補助)
※1.2.の補助については1組織1回限り、3.の運営は1.の結成補助を行った翌年度から適用する。
2 申請の手順
- 自主防災会は、市に対し補助金申請書を提出する。
- 市は、「古河市自主防災組織活動補助金交付要綱」に基づき、交付手続を行う。補助金交付に際し、交付決定通知書を送付する。
- 自主防災会は、補助事業が完了した日から30日を経過した日または、当該年度の3月31日までに実績報告書、関係書類を市長に提出する。
補助対象事業
- 自主防災組織結成事業
補助額 1組織10万円(定額)
提出書類(申請) 結成申請書、規約、年間事業計画書、予算書
提出書類(実績報告) 決算書、防災カルテ、防災マップ - 資機材等整備事業
補助額 1組織40万円(限度額)(1/2補助)
提出書類(申請) 年間事業計画書、予算書、資機材の見積書(写)
提出書類(実績報告) 決算書、資機材の請求書(写)、購入品の写真 - 運営事業
補助額 1組織3万円(定額)(1/2補助)
提出書類(申請) 年間事業計画書、予算書
提出書類(実績報告) 決算書
自主防災組織の活動
1 平常時の防災意識の啓発や高揚活動について
- 防災講習会、座談会などの集会の開催
- 地域防災マップ(危険箇所の点検)の作成、避難ルートや集会所の継続的点検
- 地域の高齢者や障害者に対するアプローチ
- 災害発生時の地域の情報収集、伝達方法の研究
- 資機材の整備、保守管理
2 平常時の各種訓練の実施や参加協力について
- 初期消火訓練、避難誘導訓練、応急手当などの防災訓練
- 心肺蘇生法などの救命講習
3 災害発生時の防災活動
- 出火防止をはじめ被害抑制、混乱回避、秩序維持を図る迅速的確な広報活動
- 負傷者救出、搬送等救護活動の実施や負傷者の発生状況の把握
- 避難ルートの安全確認や高齢者世帯の安全確認、支援
自主防災組織育成事業について
自主防災組織関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 消防防災課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-77-1511
消防防災課へのお問い合わせ












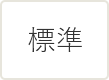
更新日:2022年05月11日