長期優良住宅認定申請
1.長期優良住宅の認定の申請を予定している方へ
長期優良住宅の認定基準には、『住居環境の維持および向上への配慮に関する基準』があります。これは法律の基本方針で、地域のまちなみ等との調和や住居環境の維持等を定めているもので、当該地区の制限に適合しない場合や、都市計画施設の区域内は原則認定できません。
以下の区域につきましては、事前に建築指導課との協議が必要となります
- 申請地が当該地区計画の区域
・古河駅東部地区地区計画(緑町、旭町二丁目、東本町四丁目、下山町、南町、三杉町一丁目、西牛谷、下辺見、上辺見、大堤の各一部)
・旭町一丁目地区地区計画(旭町一丁目、三杉町一丁目地内)
・牛谷地区地区計画(西牛谷、東牛谷地内)
・古河駅南地区地区計画(古河市古河地内) - 都市計画法第4条第6項による都市計画施設区域
- 都市計画法第4条第7項による市街地開発事業の区域
地区計画区域、都市計画施設区域、市街地開発事業の区域、につきましては、下記リンクファイルをご覧ください。 当該地域につきましては、都市計画課まで問い合わせてください。
長期優良住宅の認定につきましては、建築指導課まで問い合わせてください。
生活べんりMAP([都市計画統括図]→[都市計画決定]を選択(別ウィンドウで開きます))
古河市_都市計画課_地区計画に関するホームページ(別ウィンドウで開きます)
2.認定申請を行う際、ご注意いいただきたいこと
- 申請書第一面の宛名は「古河市長」としてください。
- 申請書第二面【6.建て方】【一戸建ての住宅の場合:各階の床面積】に入力する各階の床面積は、「階段室の部分を除いた面積」としてください(建築確認申請書に記載する床面積と異なる数値になります)。また、その床面積の求積図、計算式を添付の設計図書に明記してください。
- 「居住環境チェックシート」(茨城県等に提出する場合に必要な様式)については、古河市に認定申請する場合、不要です。
- 工事着手前に認定申請を行ってください。工事着手後は認定することができませんのでご注意ください。
※長期優良住宅の認定において、「居住面積」は生活空間を少なくとも一つの階で有効に40平方メートル以上確保することを求められています。そのため上下階への移動空間となる階段は、「居住面積」から除くこととなっています。ただし、階段下をトイレや収納等に利用した場合は、当該面積を参入します。
※茨城県の長期優良住宅のホームページにも、認定申請書の記入例が掲載されていますので、そちらもご参照ください。
【参考】茨城県の長期優良住宅に関するホームページ(別ウィンドウで開きます)
3.認定申請手数料について
下記手数料表をご確認ください。表中に記載のない申請手数料につきましては、直接お問合せ頂きますようお願いします。
長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料 (PDFファイル: 737.8KB)
4.認定申請に必要な提出書類
認定申請は正本、副本各一部、合計二部提出をお願いします。
- 認定申請書
- 登録住宅性能評価機関が発行する技術的基準等の「確認書」または、「住宅性能評価書」の「写し」
- 確認済証の写し(建築基準法第6条第1項、同法第6条の2第1項に規定するもの)
- 維持保全計画書
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 床面積求積図(※上記、「2.認定申請を行う際、ご注意いいただきたいこと」参照)
- 二面以上の立面図
- 断面図又は矩計図
- 委任状(任意様式 ※押印欄が設けられた様式の場合、押印をお願いします。)
5.工事完了報告書を提出される方へ
報告書に記載する認定実施者の住所及び連絡先は、新居となる新しい住所(住居表示)、その電話番号を記入してください。固定電話の番号が未確定の場合は携帯電話の番号を記入してください。住居表示地区の場合、確定した住居表示を記入ください。(認定申請時の旧住所、連絡先のみ記入しての報告はしないようにお願いします。(新住所と旧住所を併記は可。))
工事完了報告書に下記書類の添付をお願いいたします。
・1-1 工事監理報告書(建築士法施行規則第17条の15に基づく第4号の2様式)の写し
または
・1-2 登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し
・2 検査済証の写し(建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項に規定するもの)
・3 委任状(任意様式 ※押印欄が設けられた様式の場合、押印をお願いします。)
6.長期優良住宅の認定を受けられた方へ
【配布チラシ】認定を受けられたみなさまへ (PDFファイル: 137.6KB)
【配布チラシ】長期優良住宅完了報告のお知らせ (PDFファイル: 287.1KB)
認定後に行っていただくこと
計画どおりに住宅のメンテナンスをしましょう
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。
建築やメンテナンスの記録を保存しましょう
認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。
メンテナンス記録の報告をお願いします
認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、所管行政庁より調査を行うことがあります。(法第12条) その他、必要に応じて、所管行政庁が同様の内容について報告を求めることがあります。調査依頼が届きましたら早めの報告にご協力をお願いします。
建築又は維持保全に関する報告書 (Wordファイル: 15.0KB)
認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書 (Wordファイル: 19.5KB)
こんなときは手続きが必要です
認定を受けた計画を変更しようとするとき
認定を受けられた方は、認定を受けた計画を変更するときは、あらかじめ所管行政庁の認定を受ける必要があります。(法第8条第1項) ※建築だけでなく維持保全に関する部分を変更しようとする場合も同様です。
変更認定申請の場合の提出書類
- 変更認定申請書
- 「確認書」、または「住宅性能評価書」の「写し」 ※変更により技術審査をやり直した場合
- 確認済証の写し ※変更により確認申請をやり直した場合
- 変更した設計図書(変更部分がわかるように表記された変更前と変更後の図書)
- 委任状(任意様式)※申請者本人以外の方が手続きをする場合
※この変更申請には、所定の手数料が必要となります。
法第5条第3項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲受人を決定した日から3カ月以内に、譲受人と共同して所管行政庁に変更の認定を申請してください。(法第9条第1項)
譲受人決定の場合の提出書類
- 変更認定申請書
- 登記簿謄本の写し、または売買契約書等の写し ※名義変更が行われたことのわかる資料
- 以前に受けた認定通知書の写し
- 委任状(任意様式)※申請者本人以外の方が手続きをする場合
※この変更申請は、手数料が不要です。
【注意】譲受人の欄には、新居となる新しい住所(住居表示)、その電話番号を記入してください。固定電話の番号が未確定の場合は携帯電話の番号を記入してください。住居表示地区の場合、確定した住居表示を記入ください。(認定申請時の旧住所、連絡先のみ記入しての報告はしないようにお願いします。(新住所と旧住所を併記は可。))
認定長期優良住宅を相続や売買するとき
相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承認が必要となります。(法第10条)
地位の承継の場合の提出書類
- 変更認定申請書
- 登記簿謄本の写し、または売買契約書等の写し ※名義変更が行われたことのわかる資料
- 以前に受けた認定通知書の写し
- 委任状(任意様式)※申請者本人以外の方が手続きをする場合
※この変更申請は、手数料が不要です。
【注意】譲受人の欄には、新居となる新しい住所(住居表示)、その電話番号を記入してください。固定電話の番号が未確定の場合は携帯電話の番号を記入してください。住居表示地区の場合、確定した住居表示を記入ください。(認定申請時の旧住所、連絡先のみ記入しての報告はしないようにお願いします。(新住所と旧住所を併記は可。))
ご注意いただきたいこと
所管行政庁による維持保全の状況調査
工事完了の報告など、認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、所管行政庁より、一部の方を対象に調査を行うことがあります。(法第12条) その他、必要に応じて、所管行政庁が同様の内容について報告を求めることがあります。 ※所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、または虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
認定の取消し
以下の場合に該当すると、所管行政庁から認定を取り消されることがありますので、留意してください。(法第14条第1項)
- 認定を受けられた方が計画に従って建築・維持保全を行わず、所管行政庁に改善を求められ、従わない場合。
- 認定を受けた分譲事業者の方が譲受人を決定しない、または決定しても変更の認定申請をしていないことにより、所管行政庁に改善を求められ、従わない場合。
なお、新築時に長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金の交付を受けている場合、認定が取り消されると、補助金の返還を求められますので、留意してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 建築指導課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
建築指導課へのお問い合わせ












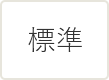
更新日:2024年04月01日