後期高齢者医療保険の自己負担限度額
75歳以上の人、および一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人が、後期高齢者医療制度の被保険者となります。これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
医療費の自己負担割合
令和4年10月1日から後期高齢者医療制度の制度改正に伴い2割負担が創設され、医療費の窓口負担割合は1割、2割、3割のいずれかになります。
| 割合 | 所得区分 | |
| 3割 | 現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得【注1】が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人 |
| 2割 | 一般2 |
(1)被保険者が世帯に一人の場合 住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入額+ その他の合計所得金額の合計が200万円以上 (2)被保険者が世帯に二人以上の場合 住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入額+ その他の合計所得金額の合計が320万円以上 |
| 1割 | 一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の人 |
| 低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人) | |
| 低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員の一人ひとりの所得が0円になる人 | |
現役並み所得者の判定基準は、「世帯内に住民税課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者がいる人」となります。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者は、基礎控除後の総所得金額等【注2】の世帯内合計額が210万円以下であれば次のいずれかの負担区分となります。
(1)被保険者が世帯に一人の場合
・年金収入額+その他の合計所得金額が200万円以上・・・2割
・年金収入額+その他の合計所得金額が200万円未満・・・1割
(2)被保険者が世帯に二人以上の場合
・年金収入額+その他の合計所得金額が320万円以上・・・2割
・年金収入額+その他の合計所得金額が320万円未満・・・1割
【注1】住民税課税所得
収入金額から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等を差し引いて求めた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いた額です。
【注2】基礎控除後の総所得金額等
前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。
基準収入額の適用について
一部負担金の割合が「3割」となった方でも、次のいずれかの条件を満たす場合は、お住まいの市町村担当課へ申請することで、「1割」または「2割」となります。
〈2割負担になる方〉
(1)被保険者が世帯に一人の場合
・総収入【注3】の額が383万円未満であり、年金収入額+その他の合計所得金額が200万円以上
(2)被保険者が世帯に二人以上の場合
・総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入額+その他の合計所得金額が200万円以上
(3)被保険者が世帯に一人の場合で、かつ、その同じ世帯に70~74歳の方がいる場合
・被保険者及び70~74歳の方の総収入の合計額が520万円未満であり、被保険者の年金収入額+その他の合計所得金額が200万円以上
〈1割負担になる方〉
(1)被保険者が世帯に一人の場合
・総収入の額が383万円未満であり、年金収入額+その他の合計所得金額が200万円未満
(2)被保険者が世帯に二人以上の場合
・総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入額+その他の合計所得金額が200万円未満
(3)被保険者が世帯に一人の場合で、かつ、その同じ世帯に70~74歳の方がいる場合
・被保険者及び70~74歳の方の総収入の合計額が520万円未満であり、被保険者の年金収入額+その他の合計所得金額が200万円未満
【注3】総収入
「地方税法の計算上用いられる、所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)の合計額」であり、公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等を差し引く前の額です。所得金額ではありません。 収支上の損益に関わらず、確定申告をしたものはすべて上記収入金額に含まれます。
負担割合の詳細につきましては茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ 自己負担割合について 〈外部リンク〉
高額療養費について
同じ月内に医療機関窓口で支払った自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
※保険適用外の支払い(食事代等)に関しましては自己負担となります。
手続きの流れ
(1)初めて高額療養費に該当したときは、申請書を送付しますので、古河庁舎国保年金課、又は総和庁舎市民総合窓口課、三和庁舎市民総合窓口室の窓口にて手続きを行ってください。
(2)2回目以降の該当のときには、申請手続きは不要です。1回目に申請いただいた口座にお振込みいたします。
【窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置について】
令和4年10月1日の施行後3年間 (令和7年9月30日まで)は、2割負担となる被保険者について、窓口負担割合の見直しに伴う1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用による払い戻しがある場合は、高額療養費として支給されます。
令和7年9月30日の配慮措置の終了後は、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えるための医療機関等の窓口での上限や、差額の払い戻しがなくなります。
配慮措置の終了については、厚生労働省がコールセンターを設置しておりますのでご活用ください。
【厚生労働省コールセンター】
・電話番号 0120-117-571(フリーダイヤル)
・設置期限 令和8年3月31日(火曜日)まで
※日曜日、祝日、年末年始は除く
・対応時間 午前9時~午後6時
自己負担限度額や配慮措置の詳細につきましては、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ 高額療養費 〈外部リンク〉
入院時の食事代
入院したときは、医療費のほかに食事代等の自己負担があります。
[入院時の食事代の自己負担額(1食当たり)]
|
所得区分 |
|
令和7年3月までの診療分 |
令和7年4月からの診療分 |
|
現役並み所得者と一般 |
|
490円 |
510円 |
|
指定難病患者 |
280円 |
300円 |
|
|
低所得者2 |
90日までの入院 |
230円 |
240円 |
|
90日を超える入院(※1) (過去12か月の入院日数) |
180円 |
190円 |
|
|
低所得者1 |
|
110円 |
110円 |
低所得者1、低所得者2の所得区分に該当される方が食事代の減額を受けるには、医療機関窓口で限度区分の記載がある資格確認書の提示またはマイナ保険証の利用が必要です。
(※1)低所得者2の所得区分に該当される期間で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は申請により食事代が減額されます。
あとから費用が支給される場合
次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、市町村の窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
- やむを得ない理由で、資格確認書またはマイナ保険証を持たず受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき(海外渡航中の治療を含む)
- 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具がかかったとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 緊急、その他やむを得ず医師の指示があり、重病人の入院・転院などの移送に費用がかかったとき(移送費の支給)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ












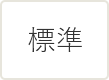
更新日:2025年08月01日