地震が起きたら
地震の瞬間・直後にケガをしないことが重要です。
1.地震の瞬間

- 揺れを感じたら低い姿勢をとり、周囲の丈夫な机やテーブルの下に隠れたり、クッションや本などが身近にあれば、頭の上にもっていき頭部を保護しましょう。
- 揺れている最中は、無理に屋外に出ようと慌てて動かず、周囲の状況を確認し、「物が落ちない・倒れない」場所に移動しましょう。
- 地震により扉が開かなくなる場合があります。扉を開けて避難経路を確保しましょう。
外出先で地震が発生したら

- タイル壁やガラス窓、陳列棚等の近くにいる場合は、周囲を確認してすぐに離れましょう。
- エレベーターに乗っていた場合には、全ての階層のボタンを押し、止まった階層でおりましょう。
車に乗っていたら

- 大きな揺れを感じたら、急ブレーキや急ハンドルは避け、前後を走る車に注意しハザードをつけて徐々に速度を落とし、安全な方法で道路の左側に寄せて停車しましょう。
2.揺れがおさまったら
- 家族の安否を確認し、怪我をしているならば応急手当をしましょう。
- 地震直後は割れたガラスや食器などが散乱しているおそれがあります。家の中であっても厚いスリッパや靴などを履き、軍手などを付けて行動しましょう。
- 夜間に発生し停電に見舞われた場合は、懐中電灯やスマートフォンのライト機能などで視界と安全を確保してください。
- 調理器具や暖房機器などの火気の確認をしましょう。
- 家屋の被害状況を確認するとともに、周辺で建物火災などが発生していないか確認してください。
~やってはいけないこと~
- 地震直後はガス漏れの危険があります。安全が確認できるまでは、火は使わないようにしましょう。(ろうそくの使用も避けましょう)
- 停電している場合、通電の際に火災のおそれがありますので、電灯、電気器具などのスイッチは入れないようにしましょう。(ブレーカーを落としておきましょう。)
3.情報を入手

- 今後の行動を決めるためにも、情報は重要になります。テレビやラジオ、スマートフォンなどで積極的に情報を取得しましょう。
- 大きな災害が発生すると、真偽不明な情報がメールやSNSなどでインターネット上に溢れます。また、AIの活用などにより巧妙化しています。公共の情報で確認を取るよう心がけ、未確認の情報は拡散しないようにしましょう。
4.避難
地震の場合には、自宅の安全性が確保されているならば避難所などへの避難は必ずしも必要ありません。避難所での生活は環境の変化が大きいため体調を崩しやすくなりますので、「在宅避難」を考えましょう。
(1)避難の判断

- 自宅の損壊が大きく、余震などで倒壊する恐れがある場合や周囲に危険な要素がある場合などには避難をしてください。(ヒビが入っている、傾いている、隣家が傾いている、地盤沈下が起きているなど)
- 近隣で火災やガス漏れがあり、延焼の恐れがある場合は速やかに避難してください。 この場合は、一時的に安全な場所(避難場所など)に避難し、火災の危険がなくなるのを確認しましょう。
(2)在宅避難をされる場合
- 余震の発生に備え、自宅内に活動の拠点となる安全なスペースを1か所確保しましょう。
- 近所の方や地域自治組織に対し「ここにいます」を発信してください。
- 情報から孤立しないようにしましょう。特にご近所とのつながりは重要です。
- 支援物資は避難所に届くこととなります。必要があれば近くの避難所に在宅避難をしていることを連絡してください。(支援物資は避難所または指定する場所での受け渡しとなります。)また、公的な支援情報なども避難所で掲示されることになります。
- 少なくとも3日間は、支援が来ないことを想定して避難時の生活設計を立てましょう。
(3)避難所へ避難される場合
- 家から離れる時には、ブレーカーを落とし、ガスの元栓は閉めましょう。
- 家族や知人にSNSや災害用伝言ダイヤル「171」などを用いて連絡先を伝えましょう。
- 避難所へは食糧や日用品などの必要なものを持参しましょう。
- 避難所へ着いたら受付を行います。自分たちの所在・安否を明確にしましょう。

- 避難所では多くの方と共同生活を行うこととなります。ルールーやマナーを守り、助け合いながら生活をしましょう。
- 避難所運営は避難者の「自治」が基本です。開設当初は市の職員が運営に関与いたしますが、つとめて早期に避難者による自治組織を立ち上げ運営に移行します。進んでの運営に協力をするようにしましょう。
(4)車内で避難生活(車中避難)をされる場合
車中避難ができる場所は避難所・避難場所の駐車場に加え、下記リンクを参照ください。
- 支援物資は避難所に届くこととなります。必要があれば近くの避難所に車中避難をしていることを連絡してください。(支援物資は避難所または指定する場所での受け渡しとなります。)また、公的な支援情報なども避難所で掲示されることになります。
- 長時間車内で同じ体勢でいることによりエコノミークラス症候群が発症しやすくなります。適時の水分補給と屈伸運動などを行うことで発症を抑制することができます。
これら以外に、親戚・友人宅へ身を寄せるなども選択肢に含めましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 消防防災課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-77-1511
消防防災課へのお問い合わせ












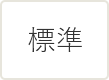
更新日:2025年12月12日