令和7年度後期高齢者医療の保険料
令和7年度保険料率
| 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額(上限) |
| 47,500円 | 9.66% | |
| 80万円 |
保険料は高齢化等による医療費の増加等を反映し、2年ごとに見直されます。
なお、県内は均一の保険料率です。
個人ごとの保険料額の決めかた
1年間の保険料額(100円未満切り捨て)
=均等割額47,500円+所得割額(賦課のもととなる金額)×9.66%
注釈:賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除額
注釈:総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。
注釈:基礎控除額とは、地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円)となります。
保険料の軽減措置
所得の低い人は、保険料が次のように軽減されます。
なお、軽減に当たって皆さんにあらためて手続きをしていただく必要はありません。
均等割額の軽減
| 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合算額が次の場合 | 軽減割合 |
| 43万円+「10万円×(給与所得者の数-1)」以下の世帯 | 7割 |
|
43万円+「10万円×(給与所得者の数-1)」 +「30万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
5割 |
|
43万円+「10万円×(給与所得者の数-1)」 +「56万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割 |
注釈:収入が公的年金のみの人は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の人は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
注釈:給与所得者の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人をいいます。
その他の軽減
いままで「会社などの健康保険の被扶養者」であった人は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減され所得割額の負担はありません。(注意:国民健康保険または国民健康保険組合の加入者であった人は、該当しません)
加入後2年間が経過し、被扶養者の軽減措置が終了した人は、世帯の所得水準に応じて均等割額の軽減を受けることができます。なお、所得割額は引き続きかかりません。
保険料の納付方法
後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険と同様に原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、次の条件に該当する人は、市役所からお送りする納付書による納付(普通徴収)となります。
- 受給している年金額が年額18万円未満の人
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が、年金受給額の2分の1を超える人
- 年度途中で後期高齢者医療制度に加入された人
- 軽減により前年度途中で保険料の賦課・徴収が中止された人
- 介護保険料が特別徴収となっていない人
- 年金が支払調整、差止、支給停止になっている人
特別徴収の人
前年の所得が確定するまで(4月・6月・8月)は前々年の所得をもとに仮算定による金額が徴収され(仮徴収)、所得確定後(10月・12月・2月)は年間保険料の額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて徴収されます。前年の所得が確定したことにより10月以降に徴収される保険料の額が決定したときは、「後期高齢者医療保険料額特別徴収額通知書」が送付されます。
普通徴収の人
7月に保険料額決定通知兼納入通知書が送付されます。
所得確定後、7月~翌年2月まで8期の納期により納めていただきます。
特別徴収から普通徴収へ支払い方法の変更方法
後期高齢者医療制度の保険料を特別徴収(年金天引き)によって納付される人で、口座振替による納付(普通徴収)を希望される人は、申出により納付方法を特別徴収から普通徴収に変更することができます。
なお、いずれの方法によっても年間の保険料総額は変わりません。
また、特別徴収の継続を希望される人は、申出の必要はありません。ただし、申出前の保険料の納付状況等によって、口座振替への変更が認められない場合があります。
【必要なもの】
- 資格確認書
- 認印(金融機関届出印)
- 金融機関の通帳
- 口座振替依頼書の控え(事前に金融機関に申し込みをした場合)
[申請場所]
- 古河庁舎 国保年金課【電話0280-22-5111(代表)】
- 総和庁舎 市民総合窓口課【電話0280-92-3111(代表)】
- 三和庁舎 市民総合窓口室【電話0280-76-1511(代表)】
注意:保険料の支払方法を口座振替に変更した後において、保険料の未納が続いた場合、特別徴収に変更される場合があります。
注意:特別徴収を普通徴収に変更するまでに一定の期間が必要となります。 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った人に適用されます。
普通徴収者の口座振替申し込み
普通徴収の保険料は、市内金融機関、市役所の会計窓口またはコンビニエンスストアで納付することができますが、確実かつ安心な口座振替をお勧めします。
保険料の納付を世帯主や配偶者等の口座振替にした場合、所得税等に係る社会保険料控除は、口座振替により納付された人に適用されます。これにより、世帯全体の所得税額や住民税額が少なくなる場合があります。
手続きに際しては、口座振替依頼書の提出が必要になりますので、次のものをご持参のうえ、市内金融機関、古河庁舎国保年金課、総和庁舎市民総合窓口課、三和庁舎市民総合窓口室において手続きを行ってください。原則として、手続きが済んだ翌月から振替ができます。
- 振替口座の通帳
- 認印(金融機関届出印)
保険料の減免
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が居住する住宅・家財に損害を受けた場合で、その損害の割合(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が1000万円以下の人は、災害を受けた日以降に到来する当該年度の納期において納付すべき保険料について、次の表に掲げる割合により軽減、または免除されます。ただし、申請が必要です。
| 前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
|---|---|
| 500万円以下 | 2分の1 |
| 500万円を超え750万円以下 | 4分の1 |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 |
| 前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
|---|---|
| 500万円以下 | 全部 |
| 500万円を超え750万円以下 | 2分の1 |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 4分の1 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ












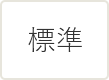
更新日:2025年08月01日