三和資料館 展示室案内
開催中の展覧会
第34回 古河市小学生古文字書道展(三和地区小学校小学生3年~6年生の作品展)
(主催:篆刻美術館)
三和地区小学校小学生3年~6年生が漢字の古い書体である篆書体(てんしょたい)に挑戦しました。その作品を展示します。
- 会 期:1月25日(日曜日)~2月23日(月曜日・祝日)
- 開館時間:午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)
- 入 館 料:無 料
- 休 館 日:1月26日(月曜日),1月30日(金曜日),2月2日(月曜日),2月9日(月曜日),2月12日(木曜日),2月16日(月曜日)
各学校ごとに作品の展示期間が異なります。
| 回 | 小学校名 | 展示期間 |
| 1 | 諸川小 | 令和8年1月25日(日曜日)~2月1日(日曜日) |
| 2 | 駒込小・大和田小 | 令和8年2月3日(火曜日)~2月8日(日曜日) |
| 3 | 仁連小 | 令和8年2月10日(火曜日)~2月17日(火曜日) |
| 4 | 名崎小 | 令和8年2月18日(火曜日)~2月23日(月曜日・祝日) |
過去の展覧会(この展覧会は終了しました)
ミニ展示2026 午年にちなんで
新年を迎え、令和8年(2026)の干支丙午(ひのえうま)にちなみ、午=馬および午年に関連した資料を展示します。
- 会 期:(終了しました)令和8年1月7日(水曜日)~1月22日(木曜日)
- 開館時間:午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)
- 入 館 料:無 料
- 休 館 日:1月13日(火曜日)・1月19日(月曜日)

ご あ い さ つ
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
三和資料館では、平成24年(2012)1月以来、その年の干支にちなんだミニ展示を開催しており、令和8年も午年にちなんだ展示を開催することといたしました。
午は、十二支の7番目にあたり、動物としては馬が当てられます。馬は、警戒心が強い一方、おとなしく素直で、人が愛情を持って扱えば信頼し、命令にもよく従うことから飼育しやすく、日本でも古くから軍事用や移動用のほか、荷物運搬用の家畜としても重要視されてきました。
馬と深く関わってきた人々は、飼っていた馬が亡くなると、供養のために馬頭観音の石仏を造立しました。特に、日清・日露戦争において多くの馬が軍馬として徴用され、戦地で命を落とした馬の供養として、馬頭観音とともに「馬霊神」「馬頭尊」と刻まれた石碑が各地で造立されています。
今回のミニ展示も、午=馬にちなんだ資料をはじめ、これまで同様、午年に起きたさまざまなできごとや、それに関連する資料・写真類を展示しており、時代的にも江戸時代初期から平成期までかなり幅広く扱っています。この展示を通して、これまで午年にどのようなことが起こったのか、どんなものが世に出されたのかを振り返っていただければ幸いです。
結びに、令和8年の午年が平穏無事に、そしてすべての皆様が幸せな一年でありますことを心からお祈りいたします。本年も、図書館ともども博物館・美術館・資料館をご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
令和8年1月
古河市三和資料館
第36回館蔵資料展「古文書でみる東諸川鈴木家~大戸新田・成田新田、そして不二道信仰~」
東諸川鈴木家は明治時代に人民総代・連合町村会議員・消防組頭などをつとめるとともに、明治16年(1883)には大戸新田・成田新田(現:八千代町大戸新田・成田)を取得し、大地主として手広く小作経営を展開しました。
また、江戸時代後期の文政11年(1826)、不二孝(不二道)の熱心な信者であった鈴木松蔵が、講仲間6名と富士山に登山(富士登拝)し、その14日間にわたる旅の様子を日記「富士禅定道中付」に記しています。
本展では東諸川鈴木家に残された古文書・古記録を中心に紹介します。
- 会 期:(終了しました)令和7年10月11日(土曜日)~12月21日(日曜日)
- 開館時間:午前10時~午後6時
- 入 館 料:無 料
- 休 館 日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、10月14日(火曜日)・10月26日(日曜日)・10月31日(金曜日)・11月4日(火曜日)・11月25日(火曜日)・11月28日(金曜日)

東諸川鈴木家は明治時代には人民総代・連合町村会議員・消防組頭などの村の役職をつとめました。いっぽうで、明治16年(1883)には幸手宿(現埼玉県幸手市)の豪商長島屋の9代目青木善六坦から大戸新田・成田新田(現八千代町大戸新田・成田)を取得し、地主として手広く小作経営を展開しました。
また、江戸時代後期のことですが、鈴木松蔵が富士講の一派で鳩ヶ谷宿(現埼玉県川口市)の小谷三志率いる不二孝(不二道)の熱心な同気(講仲間)でした。松蔵は文政11年(1828)6月、同気6人と富士山へ登山(登拝)し、帰路は見物・参詣のため、江ノ島・鎌倉・江戸へまわります。その14日間にわたる旅の様子は松蔵が記した日記「富士禅定道中附」からうかがい知ることができます。
この展覧会では、さまざまな古文書を通して、東諸川鈴木家の歴史をご来館の皆様とふり返りたいと思います。
最後になりましたが、展覧会の開催にあたり、鈴木家の皆様に深く感謝を申し上げます。
令和7年10月
古河市三和資料館
第31回企画展 初鍬入れ300年 飯沼新田開発~美田三千町歩への道程~
現在の古河市東部から常総市にかけて、かつて飯沼と呼ばれる長大な沼が南北に縦断していました。今回は、新田開発のスタートとなる享保10年(1725)の初鍬入れから300年という節目の年にあたることから、かつての飯沼と新田開発、その後の新田経営や維持・管理などにかかわる資料を展示・紹介します。
- 会 期:(終了しました)令和7年7月12日(土曜日)~9月15日(月曜日・祝日)
- 開館時間:午前10時~午後6時
- 入 館 料:無 料
- 休 館 日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、7月31日(木曜日)・8月29日(金曜日)

ご あ い さ つ
現在の古河市東部から常総市にかけて、かつて飯沼と呼ばれる長大な沼が南北に縦断していました。
飯沼は、『将門記』にも登場し、周辺の人びとにとって漁猟や水草採取などの場として利用されていたと考えられます。この飯沼を新田開発しようという動きは江戸時代前期には確認され、その後もたびたび計画が持ち上がりますが、反対する地元民も少なからずいたこともあってなかなか実現には至りませんでした。
しかし、江戸幕府8代将軍徳川吉宗の時代に新田開発が幕府によって奨励されたことにより、飯沼でもついに開発計画が実現することになります。実際に新田開発のスタートとなる初鍬入れ(事業開始)が行われたのが、今からちょうど300年前の享保10年(1725)1月のことでした。幕府役人・井沢弥惣兵衛などの積極的関与によって事業が進められ、2年後には約1,500町歩の新田が誕生しました。その後長く水とのたたかいを強いられながらも、地元住民のたゆまぬ努力などによって、やがて美田三千町歩と呼ばれる水田となりました。
今回は、初鍬入れから300年という節目の年にあたることから、かつての飯沼と新田開発、その後の新田経営や維持・管理などにかかわる資料を展示・紹介します。
この展示をとおして、全国的にも著名な新田開発に関わり、血のにじむような努力によって新田の維持に携わってきた人々に思いを馳せつつ、古河市域の歴史・文化への関心をさらに高めていただければ幸いです。
令和7年7月
古河市三和資料館
スポット展示 「発掘された古河 ~東の門(かど)西の門(かど)城跡~」
旧長井戸沼系大川の東側に広がる山田地区の「東の門(かど)西の門(かど)城跡」は奈良・平安時代から中世まで連綿と続く遺跡です。遺構写真や出土したさまざまな資料を展示して遺跡の概要等を紹介します。
- 会 期:(終了しました)令和7年3月29日(土曜日)~6月1日(日曜日)
- 開館時間:午前10時~午後6時
- 入 館 料:無 料
- 休 館 日:毎週月曜日(5月5日は開館)、4月30日(水曜日)・5月7日(水曜日)・5月30日(金曜日)

ごあいさつ
古河市内には、いにしえの人々が生活していた痕跡(こんせき)(遺跡)が約400か所で確認されています。これらの包蔵地と呼ばれる遺跡や古墳(こふん)・城跡などが、道路や建物の建設などさまざまな要因にともなって現状変更される場合は、事前に図面や写真記録として保存していくために発掘調査が実施されます。
今回紹介する「東の門(かど)西の門(かど)城跡」は、山田地区内の広範囲に広がる集落跡・城館跡で、県の土地改良事業にともない、平成31年1月から令和7年3月にかけて、第1次から第7次まで断続的に調査が行われました。
その結果、弥生(やよい)時代から中世にいたる、竪穴(たてあな)建物跡や掘立柱(ほったてばしら)建物跡・溝跡・井戸跡などの遺構が数多く確認され、旧石器時代後期の石器をはじめ、弥生土器・土師器(はじき)・須恵器(すえき)・陶器・磁器・土製品・石製品・鉄製品・銅製品など、さまざまな種類の遺物も出土しました(今回の展示では、第1次から第5次調査までを中心に紹介いたします)。
中でも、茨城県内でも数例しか確認されていない皇朝十二銭(こうちょうじゅうにせん)の一つ『富寿神宝(ふじゅしんぽう)』が2点出土したほか、一連の調査で、遺跡名でもある東の門西の門城跡に関わると思われる堀跡や天目(てんもく)茶碗をはじめとする陶器や磁器、鉄製品や石製品なども少なからず出土しています。
この調査で確認されたこれらの貴重な遺構や遺物は、今後の市域の歴史・文化を考えていくうえで、たいへん重要な手がかりになるものと思われますが、その一方で、この地域では古くから山田城という城館があり、戦国時代には山田大蔵(おおくら)なる人物が城主であったという伝承もあり(今井隆助『北下総地方史』等)、裏付けとなる文献資料が少ない中で、今回の調査成果とこうした伝承をどのように結びつけていくかなど、多くの課題も見えてきます。
今回の展示をとおして、この地域の歴史や、いにしえの人々の暮らしぶりに思いを馳せつつ、埋蔵文化財への関心をさらに高めていただければ幸いです。
令和7年3月
古河市三和資料館
ミニ展「巳年にちなんで」
新年を迎え、令和7年(2025)の干支乙巳(きのとみ)にちなみ、巳年に関連した資料を展示します。
- 会 期:(終了しました)令和7年1月7日(火曜日)~1月19日(日曜日)
- 開館時間:午前10時~午後6時
- 入 館 料:無 料
- 休 館 日:1月14日(火曜日)

ごあいさつ
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
三和資料館では、平成24年(2012)1月以来、その年の干支にちなんだミニ展示を開催しており、令和7年も巳年にちなんだ展示を開催することといたしました。
巳=蛇は、十二支の6番目の動物ですが、ほかの十二支が実名か略して呼ばれているのに、蛇だけが「み」と呼ばれています。蛇=へびは平安時代ごろまでは「倍美=へみ」といわれ、「美」の字は「み」とも「び」とも読まれることから、「へみ」が現在の「へび」に転じたといわれ、もともとの「へみ」を略して「み」が十二支に使われるようになったといわれています。
また、蛇は古くから人との生活に深い関わりを持ち、その姿や生態から強い嫌悪感をもって避ける人も多いですが、それは神聖なものに対する禁忌ともいわれ、蛇を神聖化し、神と崇める風習が生まれるとともに、日本各地で蛇に関する信仰や伝説なども残されています。
今回のミニ展示も、巳=蛇にちなんだ資料をはじめ、これまで同様、巳年に起きたさまざまなできごとや、それに関連する資料・写真類を展示しており、時代的にも江戸時代初期から平成期までかなり幅広く扱っています。この展示を通して、これまで巳年にどんなことが起こったのか、どんなものが世に出されたのかを振り返っていただければ幸いです。
結びに、令和7年の巳年が平穏無事に、そしてすべての皆様が幸せな一年でありますことを心からお祈りいたします。本年も、図書館ともども博物館・美術館・資料館をご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
令和7年1月
古河市三和資料館
第30回企画展「宮本理三郎・中人・尚子木彫展~3代に伝わる木彫の世界~」
市内東山田で活躍する彫刻家の宮本家3代にわたり受け継がれてきた木彫作品の数々を展示・紹介します。ごく身近にある題材に息吹を感じさせる、宮本理三郎・中人・尚子氏の作品をぜひご観覧ください。
- 会 期:(終了しました)令和6年9月21日(土曜日)~12月25日(水曜日)
- 開館時間:午前10時~午後6時
- 入 館 料:無 料
- 休 館 日:9月24日(火曜日)・9月30日(月曜日)・10月7日(月曜日)・10月15日(火曜日)・10月21日(月曜日)・10月27日(日曜日)・10月28日(月曜日)・10月31日(木曜日)・11月5日(火曜日)・11月11日(月曜日)・11月18日(月曜日)・11月25日(月曜日)・11月29日(金曜日)・12月2日(月曜日)・12月9日(月曜日)・12月16日(月曜日)・12月23日(月曜日)


展示作品に不動三尊像と落款印が新たに加わりました(2024年11月1日)

不動三尊像 宮本 中人 作

「理三郎」落款印 大久保翠洞 作

古河市を代表する刻字(こくじ)家・篆刻(てんこく)家の大久保翠洞(すいとう)(1906~97)が、宮本理三郎の落款(らっかん)印として制作したものです。
第35回館蔵資料展「大和田斎藤家文書の世界~下野壬生藩の財政を支えた名主家~」
下野壬生藩(藩主鳥居家/3万石)の飛地領である山川領大和田村(現:大和田)の名主斎藤家は、壬生藩の勝手方御用をつとめ、多額の御用金上納により壬生藩の財政を支え、藩主鳥居家や重臣たちとの関係が深い豪農でした。そのため、壬生藩より苗字帯刀御免・給人格を与えられ、3万石の壬生藩では家老・年寄に次ぐ高禄の250石という、まさに上級家臣待遇を受けていました。
明治時代になっても旧藩主鳥居家とのつながりが続くいっぽうで、名望家として自由民権運動でも活躍し、幸島村長や猿島郡会議員、県会議員などをつとめました。
今回の展覧展では、斎藤家に残されたさまざまな古文書・古記録を紹介し、地域に大きな役割をはたした斎藤家の歴史を振り返ります。
- 会 期:(終了しました)令和6年7月6日(土曜日)~9月1日(日曜日)
- 開館時間:午前10時~午後6時
- 入 館 料:無 料
- 休 館 日:7月8日(月曜日)・7月16日(火曜日)・7月22日(月曜日)・7月29日(月曜日)・7月31日(水曜日)・8月5日(月曜日)・8月13日(火曜日)・8月19日(月曜日)・8月26日(月曜日)・8月30日(金曜日)
〇主な展示資料
- (大和田村・上大野村二ヶ村秣場出入裁許状)
- 書判伝授
- (斎藤所左衛門弐人扶持・帯刀御免申渡書)
- 丁亥暮 江戸壬生積写 一
- 御仕送御用金御証文扣
- 覚(年賦金元利覚書)
- (斎藤所左衛門拾人扶持・給人格申渡書)
- (斎藤所左衛門八拾石加増弐百五拾石申渡書)
- 鳥居帯刀書状
- (第二大区第三小区戸長任命辞令)
- (大和田村・下片田村・上片田村・駒込村連合戸長任命辞令)
- 鳥居忠文書翰
- 口演
- 官有原野御下地取消之義請願(写)
- (幸島村長)当選通知書

開催にあたって
大和田村斎藤家。下野国壬生藩(藩主鳥居家/3万石)の飛地領、山川領大和田村(現:大和田)で代々名主役と藩の勝手方御用をつとめました。特に、宝暦・明和年間(1751~1772)には所左衛門広当がでて、多額の御用金を用立てた功績により給人格・知行250石を与えられ、年寄・家老に次ぐ上級家臣待遇を受けます。
時代は明治へと変わり、廃藩置県で壬生藩が消滅しても、旧藩主鳥居家と斎藤家の関係は続きました。そのいっぽうで、斎藤家は地域の名望家として自由民権運動で活躍し、県会議員や郡会議員、幸島村村長などを歴任します。
この展覧会を通して「大名家の財政維持のためにこんなにも貢献し続けた名主家があった!」という驚きをご来館の皆様に感じていただければ幸いに思います。
最後になりましたが、展覧会の開催にあたり、資料のご所蔵者である斎藤家の皆様に深く感謝を申し上げます。
令和6年7月
古河市三和資料館
スポット展示「従軍日誌・軍事郵便から見る日清・日露戦争」
令和6年(2024)は、明治27年(1894)の日清戦争から130年、明治37年(1904)に始まった日露戦争から120年という年にあたり、館蔵の資料中にも従軍日誌や軍事郵便など、日清・日露戦争に関する資料が残されていることから、節目の年にあたって、両戦争の記憶を伝える資料を展示します。
- 会 期:(終了いたしました)3月30日(土曜日)~6月2日(日曜日)
- 休館日:月曜日、4月30日(火曜日)、5月7日(火曜日)、5月31日(金曜日)
- 開館時間:午前10時~午後6時
- 入館料:無料

ごあいさつ
令和6年(2024)は、明治27年(1894)に始まった日清戦争から130年、明治37年(1904)に始まった日露戦争から120年という節目の年にあたります。
明治維新後、徴兵令によって国民の兵役義務が定められ、基本的に一定の年齢層の男子国民には、兵役の義務が課せられました。さらに、明治政府による富国強兵政策のもと、維新直後から朝鮮半島や中国東北部(満州)の権益などをめぐって中国(清)やロシアと軋轢が生じ、やがてそれが日清・日露戦争へと発展していきました。
古河市域でも、少なからぬ人々がこの両戦争に従軍し、不幸にして戦死したり、戦地で病死した人もいました。当館には、応召によって戦地(主に朝鮮半島や中国大陸・台湾)に赴き、そこで実際に体験あるいは見聞したことなどを書き留めた従軍日誌や、戦地から故郷の家族などに送った軍事郵便など、両戦争に関する資料が残されています。また、市内各地においても戦病死した兵士を慰霊する石碑や墓碑なども建立されています。
こうしたことから節目の年にあたって、両戦争の記憶を現在に伝える資料を展示します。
令和6年3月
古河市三和資料館
ミニ展示「辰年にちなんで」
新年を迎え、令和6年(2024)の干支、甲辰(きのえたつ)にちなみ、 辰年に起きたさまざまなできごとに関連する資料・写真類を展示します。
- 会 期:(終了いたしました)令和6年1月6日(土曜日)~1月21日(日曜日)
- 開館時間:午前10時~午後6時
- 入 館 料:無 料
- 休 館 日:1月9日(火曜日)・1月15日(月曜日)
〇主な展示資料
- 天正8年(1580) 布施景尊官途状
- 慶長9年(1604) 仁連天神坊・恩名真殊院宛 伊奈忠次黒印状
- 正徳2年(1712) 仁連町明細帳
- 宝暦10年(1760) 恩名村明細帳
- 安政3年(1856) 丙辰年日記・大嵐吹荒見分帳
- 慶応4年(1868) 戊辰年日記・当用雑手控書留日記
- 明治37年(1904) 日露戦争写真画報
- 大正5年(1916) 東山田郷有林紀年碑・東京大角力勝負星取表
- 昭和3年(1928) 古河概観
- 昭和39年(1964) 東京五輪聖火トーチ・八俣送信所概要
- 写真パネル 関根内匠墓・倶利迦羅不動石仏・八龍神石祠・燦SUN館落成式
等
ごあいさつ
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
三和資料館では、平成24年(2012)1月以来、その年の干支にちなんだミニ展示を開催しており、令和6年も辰年にちなんだ展示を開催することといたしました。
辰=龍は、十二支の中で唯一想像上の動物ではありますが、中国では、常に水中に棲み、必要があれば天空に飛翔することができる霊力を持つとされ、そこから天と深い関係を持つ皇帝と強く結びつき、権力の象徴とされました。また、仏教を守護する八部衆の一つとされていた龍王とも結びつきました。
日本でも、海の世界、すなわち水との関係が深く、雨を降らせる能力を持つと考えられ、そこから稲作等の豊穣や富貴、雨乞いなどと結びついていきました。また、清水が湧くところや沼・池の淵など清浄な場所には龍神が棲むと考えられてきました。
今回のミニ展示は、辰=龍にちなんだ資料をはじめ、前回同様、辰年に起きたさまざまなできごとや、それに関連する資料・写真類を展示しており、時代的にも戦国時代から平成期までかなり幅広く扱っています。
これらの展示資料を基に、これまで辰年にどんなことが起こったのか、どんなものが世に出されたのかを振り返っていただければ幸いです。
結びに、令和6年の辰年が平穏無事に、そしてすべての皆様が幸せな一年でありますことを心からお祈りいたします。本年も、図書館ともども博物館・美術館・資料館をご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
令和6年1月
古河市三和資料館
第34回 館蔵資料展 「先祖の旧地・由緒をたずねて~ご先祖様さがし~」
- 会 期:(終了いたしました)10月28日(土曜日)~12月24日(日曜日)
- 開館時間:午前10時~午後6時
- 入 館 料:無 料
- 休 館 日:毎週月曜日、10月31日(火曜日)・11月24日(金曜日)・11月30日(木曜日)
〇主な展示資料
- 柑子弥五兵衛書状
- 某政栄官途状
- 地方城主家臣記(写)
- 簗田助利官途状 【古河市指定文化財】
- 布施景尊官途状
- 奉願上口上之覚(帰参赦免願い)
- 帰参願一件
- 山川氏系図
- (武州葛飾郡松伏領上赤岩村大沼新八郎由緒書)
- (結城七郎上野守氏朝幷嘉吉元年討死家臣連名録)
- 上杉謙信書状

ご あ い さ つ
ご先祖様に思いを馳せ、その事績やルーツを調べ、家系図をつくることがブームとなっていますが、それは現在に限らず、江戸時代においても同じでした。
当館の館蔵資料のなかにも、
〇先祖の旧地・由緒の衆を慕い、書状のやりとりをした古河公方家臣の子孫(幕臣柑子弥五兵衛と諸川町名主中村三郎兵衛)に関するもの。
〇中世の豪族山川氏本家(越前山川家)と分家(恩名山川家)の子孫同士の再会と越前福井藩帰参運動に関するもの。
〇戦国期の地侍の流れをくむ名主クラスの人々の官途状(児矢野氏・鈴木氏など)や由緒書。
などがあります。
本展覧会では、江戸時代の「ご先祖様さがし」「由緒を語る」人々の資料を紹介します。先祖を慕い、後世に大昔の事実を探し求めるという、難解中の難解に取り組んだ人々の由緒にこめた想いを、ご来館の皆様に感じていただければ幸いです。
令和5年10月
古河市三和資料館
第29回企画展 「古河の古墳~久能向原(くのうむかいはら)古墳群を中心に~」
- 会 期:7月1日(土曜日)~10月1日(日曜日)【終了しました】
- 開館時間:午前10時~午後6時
- 入 館 料:無 料
- 休 館 日:毎週月曜日(※ただし、7月17日(月曜日)と9月18日(月曜日)は祝日開館します)、7月18日(火曜日)・8月31日(木曜日)・9月19日(火曜日)・9月29日(金曜日)
市内には約30か所で古墳・古墳群が確認されていますが、そのうちの一つ久能向原古墳群が倉庫建設にともなって、令和元年(2019)6月から10月にかけて発掘調査が行われました。円墳3基からなる古墳群は、調査の結果、終末期の古墳群で、いずれも著しくこわされてはいたものの複室構造の横穴式石室であることが確認され、破壊や盗難をまぬがれた副葬品が多数出土しました。
本展では、発掘調査で出土した銅鋺・耳環(じかん)・玉類・鉄刀・馬具などの副葬品を展示し、あわせて市内の古墳・古墳群や、そこから出土したとされる勾玉・鉄剣などの遺物や関連資料などを紹介します。

ご あ い さ つ
3世紀以降、各地で強大な武力と財力を持つ者が現れ、そうした豪族は地域の支配者として勢力を伸ばし、権力の象徴として土を高く盛り上げた墳丘(ふんきゅう)をもつ墓を造るようになりました。これが古墳(こふん)と呼ばれるものです。古墳は畿内(きない)の大和(やまと)王権の勢力拡大とともに全国に広がっていきました。
現在市内には、滅失も含めて30か所以上で古墳・古墳群が確認されており、そのうちの一つ、久能向原(くのうむかいはら)古墳群では令和元年(2019)、倉庫建設にともない発掘調査が実施されました。
宮戸川から小支谷の南面にあたる台地上に位置する久能向原古墳群は、円墳3基が互いに接近し合いながら所在していました。発掘調査の結果、著しく壊されてはいましたが、角閃石安山岩(かくせんせきあんざんがん)を用いた複式構造の横穴式石室が確認され、耳環(じかん)・刀子(とうす)・馬具をはじめとする副葬品が出土しています。
今回の展示では、久能向原古墳群の発掘調査で出土した副葬品等の遺物をはじめ、市内で確認されている古墳・古墳群や、そこから出土したとされる遺物や関連資料などを紹介します。
今回の展示を通じて、古代の歴史に想いをはせるとともに、埋蔵文化財への関心を持っていただければ幸いです。
最後になりましたが、本展の開催にあたりご協力いただきました方々に心より厚くお礼申しあげます。
令和5年7月
古河市三和資料館
館蔵資料展
12代将軍徳川家慶日光社参180年
「 将軍家慶日光へ参る~天保14年の社参~」
・会 期:(終了いたしました)令和5年3月28日(火曜日)~6月4日(日曜日)
・開館時間:午前10時~午後6時
・入 館 料:無 料
・休 館 日:毎週月曜日、3月31日(金曜日)、4月28日(金曜日)、5月31日(水曜日)
「 12代将軍徳川家慶(いえよし)、67年ぶりに日光社参を復活!」
日光社参は、徳川将軍家が祖家康の祥月命日4月17日にあわせて日光東照宮を参詣することで、江戸時代を通して19回(17回説もあります)実施されました。天保14年(1843)4月13日~21日、12代将軍徳川家慶の日光社参が67年ぶりに行われました。
ところで将軍家慶が日光に滞在中、周辺の要衝を警固するのが日光勤番(日光御固メ=にっこうおかため)を命じられた大名たちです。彼らは日光御成道→日光道中を進む将軍行列本隊とは別ルート(日光脇往還)である日光東街道を通行。さらに、江戸城の留守を預かる西丸大納言兼右大将(にしのまるだいなごん けん うだいしょう=将軍継嗣のこと)の名代の高家(こうけ)畠山上総介(はたけやま かずさのすけ)、将軍行列の御先手井伊掃部頭(いい かもんのかみ)もまた日光東街道を通行しました。
日光勤番大名・名代畠山・井伊の行列を迎える日光東街道の宿場町諸川・仁連両町の様子は?古文書・古記録を中心に紹介します。
主な展示資料
・日光山真図 明治33年(1900)
・日光御山之絵図 江戸後期
・東照権現様御遺状(写) 享和3年(1803)写
・道筋幷賃銭其外書上帳 天保7年(1836)
・日光御社参三海道絵図(享保13年・文政6年)
・御本陣問屋場御下宿向幷宿方入用内積書上帳 天保13年(1842)
・(御用留・手控)
・日光山御宮御参詣供奉御役人附 全 天保14年(1843)
・仁連町諸川町当分助郷帳 天保14年(1843)
・助郷人馬継立日〆帳 天保14年(1843)
・水野忠邦関札 天保13年(1842)
・パネル類(写真・図・表)
展示構成
- 描かれた日光山
- 日光山への道 ~日光脇往還「日光東街道」~
- 天保の社参~その時、日光東街道仁連町・諸川町は?~
- 家康二百回御神忌(文化12年)~将軍社参は実施せず、代参使を派遣~
- 文政の社参~幻のなった11代将軍家斉の日光社参~
開催にあたって
天保14年(1843)4月13日~21日、12代将軍徳川家慶(いえよし)の日光社参が行われなした。
日光社参は、徳川将軍家が祖家康の祥月命日4月17日にあわせて日光東照宮を参詣することをいい、約14~15万人の大行列で、日光道中を片道3泊4日かけて移動する大規模な公式行事でした。
いっぽう、古河市三和地区を南北に貫く日光東街道は、日光道中の主要な脇往還であり、日光社参の際は、将軍滞在中の日光の要衝を警固する日光勤番大名や江戸城留守を預かる将軍継嗣の名代の高家(こうけ)など多くが通行しました。そのため宿場町仁連・諸川両町には、大規模な行列通行にともなう助郷人馬継立や休息(小休・昼食)・宿泊の宿割、町役人の役割分担など関連資料が多くのこっています。
令和5年(2023)は、最後の日光社参である「天保の社参」から180年目にあたります。
この展覧会を通じて、仁連町・諸川町が日光社参にはたした役割とそれに携わった多くの先人たちに思いをはせていただければ幸いです。
令和5年3月
古河市三和資料館

ミニ展示「卯年にちなんで」
新年を迎え、令和5年(2023)の干支、癸卯(みずのとう)にちなみ、卯年に起きたさまざまなできごとに関連する資料・写真類を展示します。
- 会 期:(終了いたしました)令和5年1月5日(木曜日)~1月22日(日曜日)
- 開館時間:午前10時~午後6時
- 休 館 日:1月10日(火曜日)・1月16日(月曜日)
- 入 館 料:無 料
〇主な展示資料
- 山川領御名村年貢割付状 寛永4年(1627)丁卯10月
- 徳川家光朱印状 慶安4年(1651)辛卯10月
- 井沢弥惣兵衛(為永)書状 5月25日
- 仁連宿御継立諸御用村用留 文政2年(1819)己卯8月
- 植村出羽守(家教)関札 天保14年(1843)癸卯4月
- 丁卯年日記 慶応3年(1867)丁卯
- 公立小学校設立願書・伺い 明治12年(1879)己卯2月
- パネル類(写真・年表など)

ごあいさつ
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
三和資料館では、平成24年(2012)1月以来、その年の干支にちなんだミニ展示を開催しており、令和5年も卯年にちなんだ展示を開催することといたしました。
ウサギは、日本最古の歴史書『古事記』にも「いなばの白ウサギ」の神話として登場し、また月とウサギとの不思議な話も伝えられるなど、古くからなじみの深い動物です。
今回のミニ展示では、卯年に起きたさまざまなできごとや、それらに関連する資料・写真類を展示しており、時代的にも戦国時代から平成期までかなり幅広く扱っています。これらの展示資料をご覧いただきながら、これまで卯年にどんなことが起こったのか、どんなものが世に出されたのかを振り返っていただければ幸いです。
結びに、令和5年の卯年が平穏無事に、そしてすべての皆様が幸せな一年でありますことを心からお祈りいたします。本年も、図書館ともども博物館・美術館・資料館をご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
令和5年1月
古河市三和資料館
第33回館蔵資料展 従五位下叙位・甲斐守任官160年「幕臣 福田道昌~浪人から甲府町奉行までのぼりつめたSAMURAI~」
江戸後期~末期(幕末)の旗本福田道昌は、先祖代々の直参(幕臣:徳川将軍の家臣)ではなく、長左衛門新田(現:古河市長左エ門新田)の名主福田長左衛門の一族です。現時点では福田家当主の誰につながるか明確な資料は残っていませんが、父本左衛門は仕官を望み江戸へ出ましたが浪人。その子道昌は31歳の時、幕府勘定所役人に新規召抱、幕臣(御家人抱席=本人一代限)となり、普請役格代官手附(ふしんやくかくだいかんてつけ)に任命されました。
その後、寄場元締→徒目付→評定所留役当分助→評定所留役助と諸役職を経て、45歳の時、佐渡奉行支配組頭で御家人から旗本へと昇進。さらに、陸奥川俣代官→甲斐市川代官→甲斐甲府代官→西丸裏門番頭(布衣)と進み、安政4年(1857)4月、60歳の時、幕臣が目標のひとつとする勘定吟味役となります。現在、長左衛門新田福田家文書に残されている道昌に関する古文書・古記録は、この勘定吟味役在職中のものがほとんどです。勘定吟味役の道昌は西洋式大砲・小銃の製造御用や江戸城本丸御殿再建御用、日光山修復御用などをつとめ、文久2年(1862)には功績を認められて、従五位下甲斐守に叙位任官されました。
勘定吟味役の後は、先手鉄砲頭→甲府代官兼帯甲府町奉行(甲府勤番所管から幕府所管へ移管後の初代奉行)→二丸留守居(引退前の幕臣の名誉職)→勤仕並寄合(現役待遇の無役)と進み、70歳で隠居しました。その約8か月後には江戸幕府が滅亡しています。
今回の展示では、現存する古文書・古記録から幕臣福田道昌の功績を紹介します。
- 会 期:(終了いたしました)令和4年10月29日(土曜日)~12月25日(日曜日)
- 開館時間:午前10時~午後6時
- 休 館 日:毎週月曜日、11月4日(金曜日)・11月24日(木曜日)・11月30日(水曜日)
- 入 館 料:無 料
〇主な展示資料
- (万延度江戸城本丸御殿大奥向絵図)
- 宣旨(源朝臣道昌 任甲斐守)
- 口宣案(源道昌 叙従五位下)
- 位記(源朝臣道昌 告従五位下)
- (日光大猷院)御霊屋奥院幷仮拝殿絵図
- (老中申渡書)
- 大筒幷台其外御用留
- 六斤加農弾薬前車玉薬貫目幷箱仕切絵図面等取調候書付
- 大筒錐台水車其外御用留

開催にあたって
江戸の世もあと少しで終わる安政・万延・文久年間(1854-1864)、福田甲斐守道昌という幕府旗本がいました。彼は先祖代々の徳川将軍の家臣(幕臣)ではなく、長左衛門新田(現:長左エ門新田)の名主福田長左衛門の一族。31歳の時、幕府に新規召抱となり、その後、諸役職を歴任し、60歳で勘定吟味役という重要な役職に就任すると、65歳の時にはそれまでの功績が認められ、従五位下甲斐守に叙位任官されました。
本展覧会では長左衛門新田名主家ゆかりのサムライ福田道昌にスポットをあて、伝存する古文書・古記録から彼の功績を紹介します。この展覧会をとおして、現在はあまり知られていませんが、実は幕政に重要な役割を果たした「幕臣 福田道昌」の事績に光が当たるとともに、ご来館の皆様の関心をさらに高めることができれば幸いに思います。
令和4年10月
古河市三和資料館
第28回企画展 発掘された古河13「三島遺跡~奈良・平安時代の集落跡~」
県営畑地帯総合整備事業にともない、平成31年(2019)1月~3月にかけて発掘調査された古河市尾崎所在の三島遺跡について、その成果を紹介します。奈良・平安時代の集落跡からは、「大伴部」と墨で書かれた墨書土器(ぼくしょどき)や土師器(はじき)・須恵器(すえき)などの土器類、役人層が身につけた巡方(じゅんぽう)・丸鞆(まるとも)などの腰帯具、鎌・斧・釘などの鉄製品、灰釉陶器(かいゆうとうき)など多様な遺物が出土しています。
・会 期:(終了いたしました)令和4年(2022)7月2日(土曜日)~10月2日(日曜日)
・開館時間:午前10時~午後6時
・休 館 日:毎週月曜日(ただし、7月18日と9月19日は開館),7月19日(火曜日),7月29日(金曜日),8月12日(金曜日),8月31日(水曜日),9月20日(火曜日),9月30日(金曜日)
・入館料:無料

▲第28回企画展 発掘された古河13「三島遺跡~奈良・平安時代の集落跡~」ポスター
ご あ い さ つ
市内には、いにしえの人々が生活していた痕跡(包蔵地)が約400か所で確認されています。これらの遺跡や古墳・城跡などが、道路や建物の建設など、さまざまな工事にともなって現状が変更される場合は、事前に図面や写真・記録として残していくための発掘調査が実施されることがあります。
今回紹介する三島遺跡(尾崎)は、県の土地改良事業にともない、平成31年1月~3月に調査が行われました。
発掘調査の結果、竪穴(たてあな)建物跡21軒や掘立柱(ほったてばしら)建物跡(地面に直接柱を埋めて建てる建物)10棟など、調査面積の範囲に比べて多くの遺構(生活の痕跡)が見つかりました。いっしょに出土した土器の形状などから、時期的には1,300年前~1,000年前の奈良・平安時代のものと考えられます。
発掘調査では、多量の遺物(生活に使用された物)が出土しています。大部分は、当時の生活の中で煮炊きや貯蔵などに使われた土師器(はじき)や須恵器(すえき)と呼ばれる土器類ですが、なかには「大伴部(おおともべ)」と墨で書かれた墨書(ぼくしょ)土器や、役人層が身につける巡方(じゅんぽう)・丸鞆(まるとも)などの腰帯具(こしおびぐ)、鎌(かま)や斧(おの)・釘(くぎ)など鉄製品、灰釉(かいゆう)陶器など、土器以外にも多様な遺物が出土しています。
三島遺跡で確認された、これらの貴重な遺構や遺物は、今後の市域の歴史・文化を考えていくうえで、たいへん重要な手がかりになるものと思われます。
今回の展示をとおして、ぜひ、その一端を見ていただき、いにしえの人々の暮らしぶりに思いを馳せつつ、埋蔵文化財への関心をさらに高めていただければ幸いです。
令和4年7月
古河市三和資料館
スポット展示 第二回内国勧業博覧会・河鍋暁斎妙技二等賞牌受賞140年「第二回内国勧業博覧会の錦絵~猩々噴水・美術館を中心に~」
内国勧業博覧会は、明治政府によって5回開催された勧業博覧会。第2回は明治14年(1881)3月1日から6月30日まで上野公園で開催されました。古河出身の絵師河鍋暁斎はこの博覧会にい「枯木寒鴉図(こぼくかんあんず)を出品し妙技二等賞牌を受賞しています。昨年令和3年(2021)は開催の年から140年の節目の年でした。これにちなみ第二回内国勧業博覧会を描いた錦絵、とくに当時話題となった、美術館前に設置された「猩々噴水」を描いたものを中心に展示します。また、上野公園が会場となったそのほかの博覧会の資料もあわせて展示します。
- 会期:(終了いたしました)令和4年(2022)3月26日(土曜日)~6月5日(日曜日)
- 会期中の休館日:3月28日(月曜日),3月31日(木曜日),4月4日(月曜日),4月11日(月曜日),4月18日(月曜日),4月25日(月曜日),4月28日(木曜日),5月2日(月曜日),5月6日(金曜日),5月9日(月曜日),5月16日(月曜日),5月23日(月曜日),5月30日(月曜日),5月31日(火曜日)
- 入館料:無料
- 開館時間:午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)
開催にあたって
明治時代、政府によって開設された内国勧業博覧会は、国内の産業発展を促進し、魅力ある輸出品の育成が目的でした。この博覧会は五回まで開催され、うち第一回から第三回までは上野公園での開催でした。昨年令和3年(2021)は、明治14年(1881)に開催された第二回内国勧業博覧会から140年の節目の年でした。古河出身の絵師河鍋暁斎(かわなべ・きょうさい)は、この博覧会に「枯木寒鴉図(こぼくかんあず)」を出品し妙技二等賞牌(みょうぎにとうしょうはい)を受賞しています。このことにちなんで、本展覧会では第二回内国勧業博覧会を描いた錦絵を展示するとともに、内国勧業博覧後の大正・昭和時代に上野公園で開催された博覧会なども取り上げています。
第二回内国勧業博覧会では、イギリスの建築家ジョサイア・コンドルの設計による煉瓦(れんが)づくりの美術館が建てられ、美術館前の庭には猩々噴水(しょうじょうふんすい)が造られました。この噴水は、横浜真葛焼(まくずやき)の陶工宮川香山の出品作品「噴水器陶人物錦手(ふんすいきとうじんぶつにしきで)」で3メートルもある大作でした。この噴水は話題となり、猩々噴水と美術館を描いた錦絵が多く出版されました。本展ではその錦絵を10点ほど展示しています。猩々噴水の様々な描かれ方や、描かれた来場者の違いなども見ていただき、色鮮やかな明治期の錦絵をご堪能いただければ幸いに存じます。
令和4年3月26日 古河市三和資料館
ミニ展示「寅年にちなんで」
新年の干支「壬寅(みずのえとら)」にちなみ、寅年の古文書や資料のほか、おめでたい図柄の引札を展示します。
- 会 期:(終了いたしました)令和4年(2022)年1月5日(水曜日)~1月23日(日曜日)
- 休館日:1月11日(火曜日)・1月17日(月曜日)
- 入館料:無料
- 開館時間:午前10時~午後6時(入館は5時30分まで)
展示構成
- 寅年に書きました~寅年の古文書~
- 寅年の一年~寅年の暦~
- 寅年に生まれました
- 名前に「虎」の字があります
- 身体の一部が虎です~鵺~
- 兵法秘伝書「虎の巻」
- コレラを漢字で書くと?「虎列刺」
- 虎は毘沙門天の使い?
- 虎と薬師如来のコラボ~寅薬師~
- 虎の郷土玩具
- 虎を描きました~虎の絵画~
- めでたい!図柄の引札
開催にあたって
新年明けましておめでとうございます。
令和4年の干支(えと)は「壬寅」(みずのえとら)で寅年です。また、九星との組み合わせで「五黄の寅」(ごおうのとら)と呼ばれる36年に一度の年回りで「最強金運の年」とも言われます。
寅は動物では虎(トラ)が当てられます。トラは哺乳綱食肉目ネコ科ヒョウ属に分類される肉食動物で、日本には生息していませんでしたが、インド・中国などからそのイメージが輸入され、古代では天の四方を司る霊獣として、西の白虎があげられ、奈良県の高松塚古墳の壁画などに描かれています。実物の虎を見たことがない日本の絵師たちは、中国から伝わった絵画を手本にして多くの虎の絵を描いています。特に「龍虎図」として龍と対に描かれることが多くみられます。
本展覧会では、寅年にちなみ寅年の古文書、寅年の暦のほか、寅年生まれの人物や虎にかかわる人物、虎に関する信仰などを紹介します。また、「めでたい!」縁起の良い図柄の引札見本なども展示しました。
今年一年が良い年となりますよう御祈念いたします。
令和4年壬寅1月5日 古河市三和資料館
第27回 企画展 悪疫退散祈念「疱瘡~まじないから種痘まで~」
疱瘡は天然痘のことで、人類が唯一根絶した感染症です。1796年にイギリスのエドワード・ジェンナーが、牛痘の膿を利用したワクチン(牛痘苗)を発見し、牛痘種痘法によって天然痘を予防する道が開かれ普及すると、ついに1980年5月8日、世界保健機関(WHO)により天然痘根絶宣言が出されました。
江戸時代、疱瘡が流行るのは疱瘡神(疫病神)のしわざと考えられており、疱瘡にかからないための、またはかかっても軽くすむためのさまざまな疱瘡除けの「まじない」や護符、郷土玩具などがありました。疱瘡除けの信仰をあつめた寺社も多く存在し、疱瘡神を祀る石塔や石祠なども建てられました。
本展覧会では、疱瘡除けの「まじない」や護符など、また、種痘関係の資料を展示し、疱瘡と人々のかかわりを紹介します。
- 会 期:(終了いたしました)令和3年10月2日(土曜日)~12月26日(日曜日)
- 休館日:10月4日(月曜日)・10月11日(月曜日)・10月18日(月曜日)・10月25日(月曜日)・10月29日(金曜日)・11月1日(月曜日)・11月4日(木曜日)・11月8日(月曜日)・11月15日(月曜日)・11月22日(月曜日)・11月24日(水曜日)・11月29日(月曜日)・11月30日(火曜日)・12月6日(月曜日)・12月13日(月曜日)・12月20日(月曜日)
- 入館料:無料
- 開館時間:午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)
第26回 企画展 発掘された古河12「西染谷遺跡・犬塚遺跡」
平成30年11月~平成31年2月に発掘調査された古河市上和田の西染谷遺跡と犬塚遺跡の出土遺物を展示し、その成果を紹介します。
- 会 期:(終了いたしました)令和3年7月31日(土曜日)~
9月26日(日曜日)8月17日(火曜日) - 8月18日(水曜日)から中止
- 休館日:8月2日(月曜日)・8月10日(火曜日)・8月16日(月曜日)・8月23日(月曜日)・8月30日(月曜日)・8月31日(火曜日)・9月6日(月曜日)・9月13日(月曜日)・9月21日(火曜日)・9月24日(金曜日)
- 入館料:無料
- 開館時間:午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)

第32回 館蔵資料展「東京2020記念 館蔵資料にみるスポーツ~武道・相撲エトセトラ~」
三和資料館の館蔵資料から武道や相撲関係の資料を中心に紹介します。1964年に開催された東京オリンピック聖火リレーのトーチも展示します。
- 会 期:(終了いたしました)令和3年6月12日(土曜日)~7月25日(日曜日)
- 休館日:6月14日(月曜日)・6月21日(月曜日)・6月28日(月曜日)・6月30日(水曜日)・7月12日(月曜日)・7月19日(月曜日)

▲「1964年東京オリンピック聖火リレーのトーチ」
【当館(古河市三和資料館)所蔵】

▲「1964年東京オリンピック聖火リレーのトーチ(拡大)」【当館(古河市三和資料館)所蔵】
1964年(昭和39年)東京オリンピックの聖火リレーで、茨城県では10月2日から5日まで95区間に分けられ、1区間20人前後のグループでリレーしました。
古河市からは、古河市、総和村、三和村からそれぞれ7名ずつの走者が、10月2日に結城公民館に集合し、リレーに参加。古河市の走者が第一区間を走り、総和村の走者が結城市観音町バス停留所から東小塙まで1.4kmを走り、三和村の走者が川島駅前十字路から下館市伊讃美が原の1.9kmを走りました。
写真のトーチは、総和村の走者からリレー後に寄贈を受け、当時、村の教育委員会で公開していました。
木枠の四面ガラス張りのケースに収められたこのトーチは、ステンレス製で長さ55cm、直径3cm、重さ540g、鋳鉄製の黒いホルダーにこれを差し込むと1kgになるといいます。
ホルダーは工業デザイナーの柳宗理氏(1915~2011)のデザインによるものです。
第31回 館蔵資料展「ZOO 三和資料館付属動物園~館蔵資料にみる動物たち~」
三和資料館が所蔵する版本や絵画のなかには、動物を描いたものがあります。それらをピックアップし、架空の三和資料館付属動物園を開園します。
また、特別展示として、悪疫退散の願いをこめて「猩々(オランウータン)」の資料もあわせて紹介します。
展示構成
1 版本の中の小さな動物たち
当館寄託資料より、江戸時代から明治時代にかけて、主に木版で印刷された版本で、本文上部や巻末などに動物たちが描かれたものを紹介。
2 絵はがきの動物たち
明治時代後半から大正時代にかけて絵はがきのブームがおこりました。当館寄託資料の絵はがきの中から動物たちを描いたものを紹介。
3 ミミズク土偶
昭和61年(1986)に思案橋遺跡(市内下辺見)から出土したミミズク土偶と、平成7年(1995)に釈迦才仏遺跡から出土した土製仮面を紹介。
4 特別展示 悪疫退散の願いをこめて「猩々(オランウータン)」
オランウータンの和名が猩々であることにちなみ、悪疫退散の願いをこめて、8つの顔を持ち、悪疫退散させる力も持つとされる猩々を紹介。
5 絵画の中の動物たち
三和町諸川(現:古河市諸川)を拠点に多くの作品を生み出した故・福原廣画伯(1915~2003)の作品をはじめ、当館所蔵の絵画から動物が描かれたものを紹介。
-
会期:(終了いたしました)令和3年3月20日(土曜日・祝日)~5月30日(日曜日)
- 会期中の休館日:3月31日(水曜日)・4月5日(月曜日)・4月12日(月曜日)・4月19日(月曜日)・4月26日(月曜日)・4月30日(金曜日)・5月6日(木曜日)・5月10日(月曜日)・5月17日(月曜日)・5月24日(月曜日)
- 入館料:無料
- 開館時間:午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)
開催にあたって
第31回館蔵資料展では、館蔵資料に描かれた動物たちをピックアップし、架空の動物園「三和資料館付属動物園」を開園いたします。版本類の中に描かれた小さな動物たち、絵はがきに描かれた動物たち、絵画の中に描かれた動物たちを紹介します。少し偏りがありますが、ご勘弁ください。ほかに市指定文化財の縄文時代のミミズク土偶も展示します。これは実際のミミズクを表現したものではありません。ミミズクの顔のような土偶ということです。この土偶により縄文人の人間表現をみることができると思います。関連して市指定文化財の縄文時代の土製仮面も展示しました。
また、特別展示として、市内在住者の猩々コレクションより、悪疫退散の願いをこめて、「猩々(オランウータン)」の関連資料も展示しました。猩々は8つの顔を持ち、悪疫を退散させる力も持っていました。この展示は、茨城県独自の緊急事態宣言により臨時休館となり公開できなかった「緊急展示 悪疫退散祈念 赤は悪疫を退ける~赤い妖精?いや妖獣?もしかして妖怪? 猩々尽くしのパワースポット~」の展示の一部となります。
動物たちとのひと時楽しんでいただければ幸いです。
令和3年3月20日春分 古河市三和資料館
緊急展示 悪疫退散祈念「赤は悪疫を退(しりぞ)ける~赤い妖精?いや妖獣?もしかして妖怪?猩々(しょうじょう)尽くしのパワースポット~」(「茨城県独自の緊急事態宣言」の期間延長を受けて中止いたしました)
・会期:令和3年1月27日(水曜日)~2月23日(火・祝) (中止いたしました)
・会期中の休館日:1月29日(金曜日)・2月12日(金曜日)
・開館時間:午前10時~午後6時
コロナ禍のなか、悪疫退散を祈念し、悪疫を退けるとされる赤色をテーマに資料を展示します。
ミニ展示「丑年にちなんで」(1月18日より中止)
- 会期:令和3年(2021)1月5日(火曜日)~
1月24日(日曜日)1月17日(日曜日) - 1月18日(月曜日)より中止
- 会期中の休館日:1月12日(火曜日)
- 開館時間:午前10時~午後6時
令和3年の干支「辛丑(かのとうし)」にちなんだ資料を展示します。
- 丑年の日記
- 丑年の古文書
- 丑年の暦(こよみ)
- 牛に引かれて善光寺
- 福原廣(ふくはらひろし)の牛の絵
- 大高山願牛寺(だいこうさん がんぎゅうじ)由来
- 恵比寿・大黒の引札(ひきふだ)
第25回企画展 久昌院子聖権現御開帳記念「子聖権現~足腰守護の神仏~」
会期(終了いたしました):令和2年(2020)10月31日(土曜日)~12月27日(日曜日)
会期中の休館日:11月4日(水曜日)、11月24日(火曜日)、11月30日(月曜日)
開館時間:午前10時~午後6時
子聖権現(ねのひじりごんげん)は、子権現(ねのごんげん)ともいわれ、埼玉県飯能市にある子ノ権現天龍寺(天台宗)が子聖権現・子権現の根元とされています。子聖(ねのひじり)は天長9年(832)壬子年の子月子日子刻に生まれたといわれ、出羽三山で修行し各地を行脚した後、延喜11年(911)に十一面観音を祀って天龍寺を開いたといわれています。聖は「腰より下を病める者、一心に祈らば、その験を得せしめん」と誓いをたてられたことから、足腰守護の神仏として信仰をあつめました。市内には山田の久昌院の子聖権現堂があり、長谷町に子聖権現神社(子権現)があります。山田の久昌院の子聖権現堂は子年ごとに御開帳され、今年は3月15日から22日まで御開帳が行われました。この御開帳にちなみ、足腰守護の神仏として信仰されている子聖権現についてとりあげます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 三和資料館
所在地:〒306-0125 茨城県古河市仁連2042番地1
電話番号:0280-75-1511
ファックス:0280-75-1510
三和資料館へのお問い合わせ












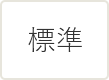
更新日:2026年01月27日