三和資料館 令和7年度 展覧会内容
スポット展示 「発掘された古河~東の門(かど)西の門(かど)城跡~」
旧長井戸沼系の大川の東側に広がる猿島台地上に立地する山田地区の「東の門西の門城跡」は、広範囲に広がる集落跡・城館跡で、県の土地改良事業にともない、平成31年1月から令和7年3月にかけて、第1次から第7次まで断続的に調査が行われました。
その結果、弥生時代から中世にいたる、竪穴建物跡や掘立柱建物跡・溝跡・井戸跡などの遺構が数多く確認され、旧石器時代後期の石器をはじめ、弥生土器・土師器・須恵器・陶器・磁器・土製品・石製品・鉄製品・銅製品など、さまざまな種類の遺物も出土しました。
今回の展示では第1次から第5次調査までを中心に遺構写真や出土したさまざまな遺物などを紹介します。
- 会期:3月29日(土曜日)~6月1日(日曜日)
- 会期中の休館日:3月31日(月曜日),4月7日(月曜日),4月14日(月曜日),4月21日(月曜日),4月28日(月曜日),4月30日(水曜日),5月7日(水曜日),5月12日(月曜日),5月19日(月曜日),5月26日(月曜日),5月30日(金曜日)
第31回企画展 初鍬入れ300年 飯沼新田開発~美田三千町歩への道程(みちのり)~
現在の三和地区の中央部には、かつて飯沼と呼ばれる長大な沼が南北に縦断していました。この飯沼を新田開発するための初鍬入れが行われたのが、今からちょうど300年前の享保10年(1725)1月のことでした。幕府役人の積極的関与によって、2年後には約1,500町歩の新田が誕生しますが、その後、長い水との戦いを強いられ、地元住民のたゆまぬ努力によって、やがて美田三千町歩と呼ばれる水田となりました。
今回は、初鍬入れから300年という節目の年にあたることから、かつての飯沼と、新田開発に関わる資料を展示・紹介します。
- 会期:7月12日(土曜日)~9月15日(月曜日・祝日)
- 会期中の休館日:7月14日(月曜日),7月22日(火曜日),7月28日(月曜日),7月31日(木曜日),8月4日(月曜日),8月12日(火曜日),8月18日(月曜日),8月25日(月曜日),8月29日(金曜日),9月1日(月曜日),9月8日(月曜日)
第36回館蔵資料展 「古文書でみる東諸川鈴木家~大戸新田・成田新田、そして不二道信仰~」
東諸川鈴木家は明治時代には村の役職をつとめるとともに、明治16年(1883)には幸手宿の豪商から大戸新田・成田新田を取得し、大地主として手広く小作経営を展開しました。そのため鈴木家には、両新田に関する資料が多く残されています。
また、江戸後期には、鈴木松蔵が富士講の一派で鳩ヶ谷宿の小谷三志率いる不二道(不二講)の熱心な信者であったため、不二道の資料も伝わります。松蔵は文政11年(1828)、講仲間と富士山に登山し、帰路は見物・参詣のため江ノ島・鎌倉・江戸へとまわっています。その14日間にわたる旅の様子は、松蔵が記した日記「富士禅定道中付」からうかがい知ることができます。
本展では、東諸川・鈴木家に残された古文書・古記録を中心に紹介します。
- 会期:10月11日(土曜日)~12月21日(日曜日)
- 会期中の休館日:10月14日(火曜日),10月20日(月曜日),10月26日(日曜日),10月27日(月曜日),10月31日(金曜日),11月4日(火曜日),11月10日(月曜日),11月17日(月曜日),11月25日(火曜日),11月28日(金曜日),12月1日(月曜日),12月8日(月曜日),12月15日(月曜日)
ミニ展示「午年にちなんで」
新年を迎え、令和8年(2026)の干支丙午(ひのえうま)にちなみ、午=馬及び午年に関連した資料を展示します。
- 会期:令和8年1月7日(水曜日)~1月22日(木曜日)
- 会期中の休館日:1月13日(火曜日),1月19日(月曜日)
第34回 古河市小学生古文字書道展(三和地区小学校小学生3年~6年生の作品展)
(主催:篆刻美術館)
三和地区小学校小学生3年~6年生の古文字書道作品を展示します。
- 会期:1月25日(日曜日)~2月23日(月曜日・祝日)
- 会期中の休館日:1月26日(月曜日),1月30日(金曜日),2月2日(月曜日),2月9日(月曜日),2月12日(木曜日),2月16日(月曜日)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 三和資料館
所在地:〒306-0125 茨城県古河市仁連2042番地1
電話番号:0280-75-1511
ファックス:0280-75-1510
三和資料館へのお問い合わせ












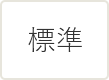
更新日:2025年10月21日