第31回企画展「初鍬入れ300年 飯沼新田開発~美田三千町歩への道程~」
第31回企画展 初鍬入れ300年 飯沼新田開発~美田三千町歩への道程~
現在の古河市東部から常総市にかけて、かつて飯沼と呼ばれる長大な沼が南北に縦断していました。今回は、新田開発のスタートとなる享保10年(1725)の初鍬入れから300年という節目の年にあたることから、かつての飯沼と新田開発、その後の新田経営や維持・管理などにかかわる資料を展示・紹介します。
- 会 期:令和7年7月12日(土曜日)~9月15日(月曜日・祝日)
- 開館時間:午前10時~午後6時
- 入 館 料:無 料
- 休 館 日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、7月31日(木曜日)・8月29日(金曜日)

ご あ い さ つ
現在の古河市東部から常総市にかけて、かつて飯沼と呼ばれる長大な沼が南北に縦断していました。
飯沼は、『将門記』にも登場し、周辺の人びとにとって漁猟や水草採取などの場として利用されていたと考えられます。この飯沼を新田開発しようという動きは江戸時代前期には確認され、その後もたびたび計画が持ち上がりますが、反対する地元民も少なからずいたこともあってなかなか実現には至りませんでした。
しかし、江戸幕府8代将軍徳川吉宗の時代に新田開発が幕府によって奨励されたことにより、飯沼でもついに開発計画が実現することになります。実際に新田開発のスタートとなる初鍬入れ(事業開始)が行われたのが、今からちょうど300年前の享保10年(1725)1月のことでした。幕府役人・井沢弥惣兵衛などの積極的関与によって事業が進められ、2年後には約1,500町歩の新田が誕生しました。その後長く水とのたたかいを強いられながらも、地元住民のたゆまぬ努力などによって、やがて美田三千町歩と呼ばれる水田となりました。
今回は、初鍬入れから300年という節目の年にあたることから、かつての飯沼と新田開発、その後の新田経営や維持・管理などにかかわる資料を展示・紹介します。
この展示をとおして、全国的にも著名な新田開発に関わり、血のにじむような努力によって新田の維持に携わってきた人々に思いを馳せつつ、古河市域の歴史・文化への関心をさらに高めていただければ幸いです。
令和7年7月
古河市三和資料館
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 三和資料館
所在地:〒306-0125 茨城県古河市仁連2042番地1
電話番号:0280-75-1511
ファックス:0280-75-1510
三和資料館へのお問い合わせ












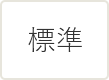
更新日:2025年07月17日