国民健康保険税の概要
国民健康保険税の使い方
国民健康保険税は、国や県などの補助金と合わせて、国民健康保険加入者の皆さんが、病気やけがをしたときの医療費や、子どもが生まれたり、家族の誰かがなくなったときなどの給付の費用に使われます。
国民健康保険税を納める人
国民健康保険税を納める人(納税義務者)は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でもその世帯に国民健康保険加入者がいれば、世帯主に国民健康保険税の納税義務が生じます。
国民健康保険税が課税される時期
保険税は月割りで計算します。届出をした月からではなく、資格が発生した月から課税されます。加入手続きが遅れると、さかのぼって課税されますのでご注意ください。
国民健康保険税の課税内容
国民健康保険税は、国民健康保険加入者の所得に応じて課税されるもの(所得割)、1人ごとに課税されるもの(均等割)の合算により計算されます。詳しくはこちらをご覧ください。
国民健康保険税の減額と軽減
低所得世帯に対する国民健康保険税の減額
国民健康保険税は、低所得世帯に対し、所得区分に応じ、均等割が7割・5割・2割軽減されます。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、所得の確認がされてない場合、軽減が受けられない場合があります。収入がない人、もしくは、障害年金や遺族年金などの非課税所得のみの人も申告をお願いします。
後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税軽減
75歳を迎えた人は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険税の税額に急激な変動が生じないようにする減額制度があります。詳しくはこちらをご覧ください。
非自発的失業者の国民健康保険税軽減
平成22年度から、解雇・倒産等の事業主の都合等、本人の意思以外により離職(失業)されている人は、申請により軽減される場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
未就学児の均等割5割軽減(国の制度)
子育て支援策として、未就学児の均等割を5割軽減します。
18歳まで(未就学児を除く)の均等割2割減免
子育て支援策として、18歳まで(未就学児を除く)の均等割を2割減免します。
産前産後期間の保険税減額
出産被保険者の産前産後期間に係る所得割と均等割を減額します。
単胎(1人出産)の場合、出産(予定)日が属する月の前月から4ヶ月間
多胎(2人以上出産)の場合、出産(予定)日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
介護保険適用除外施設入所者の軽減
介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の人が、障害支援施設等の介護保険適用除外施設に入所されている期間は、介護保険の被保険者となりませんので、介護納付金分が賦課されません。 この適用を受けるために届出が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
その他の減額
火災や天災で財産に大きな災害を受けたり、失業や事業の不振等で当該年度中の所得が皆無になったりした場合などには、申請によって国民健康保険税が減免される場合があります。また、刑事施設などの矯正施設に収容されていた場合にも減額されます。※詳しくは、国保年金課まで問い合わせてください。
国民健康保険税の納付について
国民健康保険税の納税通知書等は7月に通知します。納付方法は、納付書または口座振替で納付する普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収
普通徴収とは、送付された納付書により、納付書に記載されたコンビニエンスストア、指定金融機関、古河市役所各庁舎窓口で納める方法と、指定した預貯金口座から、金融機関などが自動的に国保税を振り替えて納付する方法があります。口座振替は、納期ごとに金融機関等にお出かけになる手間が省け、納め忘れの心配もなく便利な方法です。
特別徴収
年金から国保税を納めていただく方法です。65歳から74歳までの世帯主の方であって、条件に当てはまる人は、支給される年金から国保税を納めていただくことになります。詳しくは、こちらをご覧ください。
納税通知書が送付される前(7月)に出国される人
納税義務者が納税通知書発送(7月)前に出国する場合は、納税管理人(納税通知書の送付先)を定めてください。
国民健康保険税の社会保険料控除について
年末調整や確定申告で社会保険料控除の申告をする際に、国民健康保険税の納付額も対象となり、合計所得金額から差し引くことができます。年末調整等により、納付額を確認したい場合、11月1日から市役所各庁舎窓口等で納付額証明書を交付しています。詳しくはこちらをご覧ください。
還付金詐欺にご注意ください
「医療費や国民健康保険税の還付金があるため、振り込みの手続きをして欲しい」といった内容の不審な電話があったという情報が寄せられています。
医療費や国民健康保険税の還付金は必ず通知をお送りし、提出していただいた書類を基に振り込みをしています。
直接、ATMの操作をお願いすることはありません。また、書類の提出がないのに口座番号を聞くこともありません。悪質な犯罪の被害に遭わないよう、くれぐれもご注意ください。
少しでも不審だと感じた場合は、すぐに行動せず、連絡先を聞いて確認する時間を作ってください。
また、相手の言った連絡先が正しいと思わず、ご自身で電話番号を確認し、関連機関に問い合わせてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ












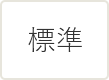
更新日:2025年11月01日